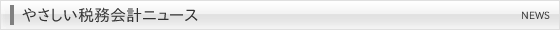
�m���k�n
 �@���͍��N�A������̍��Y�̑��^�ɂ��đ��������Z�ېł̓K�p����\��ł������A���̓͏o���̒�o�O�ɕ����S���Ȃ�܂����B
�@���͍��N�A������̍��Y�̑��^�ɂ��đ��������Z�ېł̓K�p����\��ł������A���̓͏o���̒�o�O�ɕ����S���Ȃ�܂����B
�@�����ł������������̂ł����A��L�̑��^�ɌW�鑡�^�łɂ��Ď������������Z�ېł̋K��̓K�p���悤�Ƃ���ꍇ�A���̓K�p���邽�߂ɒ�o���K�v�ȓ͏o���i���������Z�ېőI��͏o���j�̒�o��́A���̔[�Œn�̏����Ŗ������ł悢�̂ł��傤���B�����Ă��������B
�m�n
�@�����k�̏ꍇ�ɂ����鑊�������Z�ېőI��͏o���̒�o��́A�����k�җl�ł͂Ȃ��A�����l�̎��S�ɌW�鑊���ł̔[�Œn�̏����Ŗ������ƂȂ�܂��B�ڍׂ͉��L��������Q�Ƃ��������B
�m����n
�@���^�ɂ����Y���擾�����l�����̑��^�������l�̐��葊���l�i��1�j�ł���A���A���̑��^�������l�������ɂ�����60�Έȏ�ł���ꍇ�ɂ́A���̑��^�ɂ����Y���擾�����l�́A���̑��^�ɌW����Y�ɂ��āi���^�łɂ��āj�A���������Z�ېł̋K��̓K�p���邱�Ƃ��ł���ƁA�@���Œ�߂��Ă��܂��B
�@��L�̋K��̓K�p���悤�Ƃ���l�́A���̑I���ɌW��ŏ��̑��^�����N�̗��N2��1������3��15���܂ł̊ԁi���^�ł̐\�����̒�o���ԁj�ɁA�[�Œn�̏����Ŗ������ɑ��A���^�������l����̂��̔N���ɂ����鑡�^�ɂ��擾�������Y�ɂ��đ��������Z�ېł̋K��̓K�p���悤�Ƃ���|���̑����̎������L�ڂ����͏o���i���������Z�ېőI��͏o���j���A���̏��ނƂƂ��ɁA�[�Œn�̏����Ŗ������ɒ�o���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�Ȃ��A���������Z�ېőI��͏o���ɌW�鑡�^�������l����̑��^�ɂ��擾������Y�ɂ��ẮA���̓͏o���ɌW��N���Ȍ�A���������Z�ېł̋K��ɂ��A���^�Ŋz���v�Z���邱�ƂƂȂ�܂��B
��1 ���̑��^�������l�̒��n�ڑ��ł���l�̂������̔N1��1���ɂ�����18�Έȏ�ł���l�Ɍ���܂��B
�@���������Z�ېœK�p�҂����̔N���ɂ����ē��葡�^�ҁi��2�j����̑��^�ɂ��擾�������Y�ɌW�邻�̔N���̑��^�łɂ��ẮA���葡�^�҂��Ƃ̑��������Z�ېłɌW���b�T���z�i110���~�j�T����̑��^�ł̉ېʼn��i���炻�ꂼ�ꎟ�Ɍf������z�̂��������ꂩ�Ⴂ���z���T������ƁA�@���Œ�߂��Ă��܂��B
�@�Ȃ��A��L�̋K��́A�������\�����ɑ��������Z�ېł̋K��ɂ��T��������z�A���ɑ��������Z�ېł̋K��̓K�p���čT���������z������ꍇ�̍T���������z���̑����̎����̋L�ڂ�����ꍇ�Ɍ���A�K�p����ƒ�߂��Ă��܂��B
��2 ���葡�^�҂Ƃ́A���������Z�ېł̑I���ɌW�鑡�^�҂������܂��B
�@���葡�^�҂���̑��^�ɂ�葊�������Z�ېł̋K��̓K�p������Y�𑊑������Z�ېœK�p�҂��擾�����ꍇ�ɂ����āA���̓��葡�^�҂����̑��^�������N�̒��r�ɂ����Ď��S�����Ƃ��́A���̑��^�ɂ��擾�������Y�ɂ��ẮA���^�ł̐\�������o����K�v�͂Ȃ��ƁA�@���Œ�߂��Ă��܂��B
�@�������A��L�̏ꍇ�ɂ����Ă����������Z�ېł̋K��̓K�p���邽�߂ɂ͑��������Z�ېőI��͏o�����o����K�v�͂���A�܂��A����̂����k�̏ꍇ�̂悤�ɁA���^�������l���N�̒��r�ɂ����Ď��S�����ꍇ�ɂ����鑊�������Z�ېőI��͏o���̒�o�́A�ʏ�̏ꍇ�Ƃ͈قȂ�A�i���^�ɂ����Y���擾�����l�ł͂Ȃ��j���̑��^�������l�̎��S�ɌW�鑊���ł̔[�Œn�̏����Ŗ������ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƒ�߂��Ă��܂��̂ŁA�����ӂ��������B
�m�Q�l�n
���@21��9�A21��12�A28�A62�A����5�A���K11�A�[�@70��3��2�A�����21��9-2�A21��9-3�Ȃ�
�@�{���̓]�ڂ���ђ��쌠�@�ɒ�߂�ꂽ�����ȊO�̕��������ւ��܂��B

